「AIとスマート農業の未来」——研究とMulti-Sigma®活用の最前線
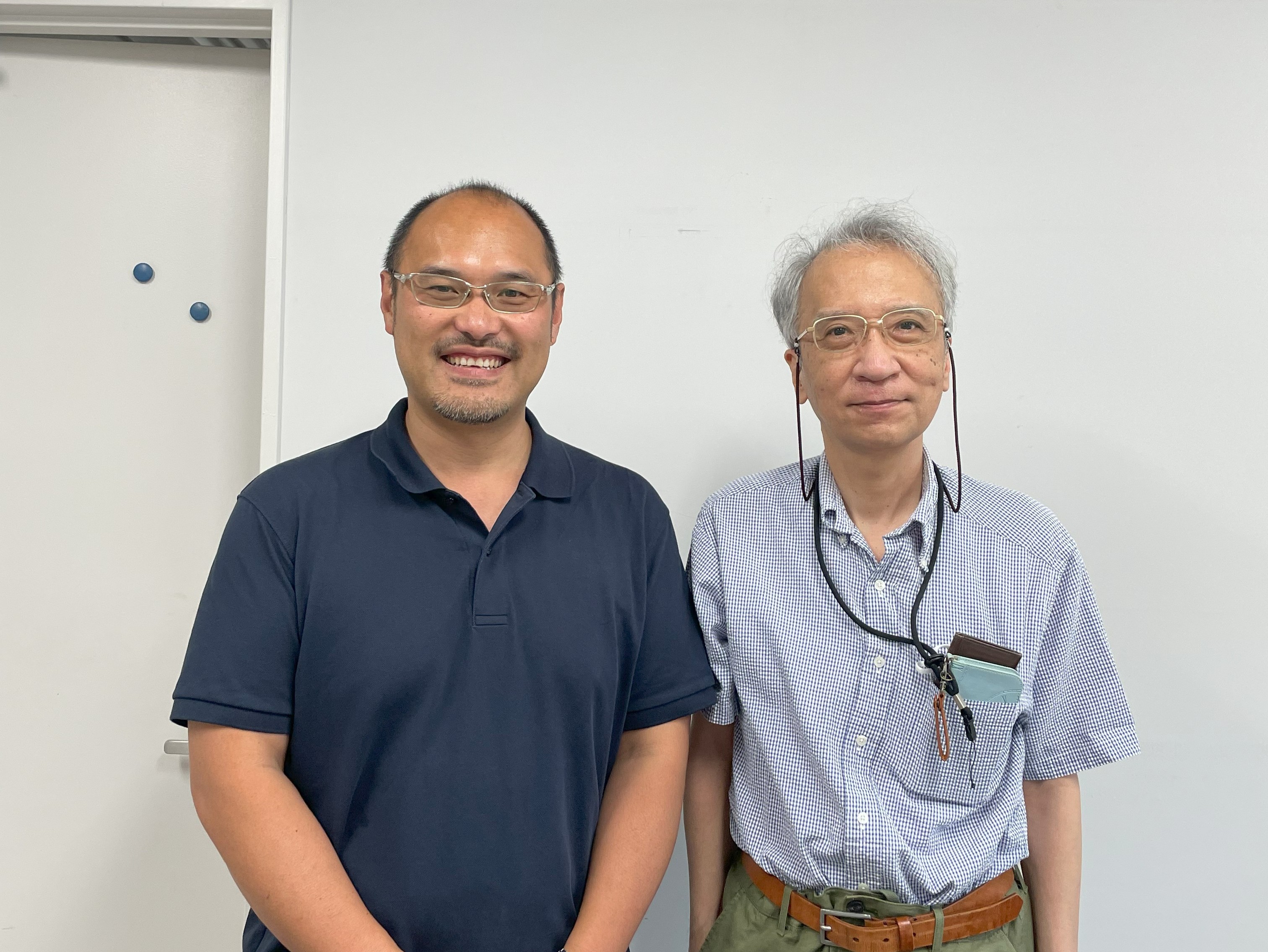
京都大学 大学院農学研究科 の長岡伸一先生は、農業分野の研究にMulti-Sigma®をご活用いただいています。今回、長岡先生とMulti-Sigma®の開発者である株式会社エイゾス河尻が対談させていただき、その具体的な活用方法について伺いました。
長岡伸一(Shinichi Nagaoka)/ 京都大学 農学研究科 地域環境科学専攻 研究員
愛媛大学理学部教授を経て、現愛媛大学名誉教授。
1983年京都大学大学院理学研究科博士後期課程修了、理学博士。
専門は、計算科学、光物理化学、反応化学。
本日はありがとうございます。早速ですが、先生がMulti-Sigma®を活用されている研究テーマについて教えていただけますか。
はい。まず背景からお話ししますと、世界的に人口が増加し、安定した高品質の農産物の供給が求められています。これまでは「今年は豊作、来年は不作」といった変動が許容されてきましたが、今後はそうはいきません。しかし安定供給にはコストや環境負荷の増大が伴います。また日本には独自の課題もあります。農家の高齢化や後継者不足、国際競争力の低下といった点です。そのため、農作物の供給においては効率化と差別化を同時に実現しなければなりません。
確かに、日本の農業は構造的に厳しい状況にありますね。そこでAIの導入が重要になるわけですね。
その通りです。農業は同じ種を蒔いても環境条件で結果が大きく異なり、非常に多様です。これまでは人間の経験や勘に頼ってきましたが、これからはデータに基づき、人間には見抜けないパターンを特定する必要があります。それによって効率化や品質向上が進み、特に小規模農家の意思決定をサポートできます。いわゆる「スマート農業」「精密農業」への転換ですね。
研究事例:卵の性判別と和牛の霜降り予測
具体的にはどのような研究にMulti-Sigma®を活用いただいているのでしょうか。
一つは鶏卵のオス・メス判別です。卵から生まれる雛は半分がオスですが、オスは卵を産まないため不要とされ、大量に殺処分されます。これは動物福祉の観点から欧州などで禁止されている国もあります。そこで、卵の神経ができる前、痛みを感じない段階で性別を判別できないかと研究しています。もし実現すれば、不要卵はワクチン原料などに活用でき、年間数十億羽規模で命が救われます。
なるほど、非常に社会的意義の大きな研究ですね。
もう一つは和牛の霜降り予測です。霜降りはビタミンAの調整など飼育方法に左右されますが、やり方を誤ると関節疾患や肉質の劣化を招きます。AIを使えば、病気リスクを回避しつつ最適な飼育条件を見つけられます。これにより、地域ごとの特色あるブランド牛の育成が可能になります。
Multi-Sigma®導入の意義
その研究にMulti-Sigma®をお使いいただいている理由を教えてください。
大きな理由は使いやすさです。クラウド計算でプログラミングが不要、入力も直感的です。以前は別の解析環境を使っていましたが、手間も多く専門知識も必要でした。Multi-Sigma®ではコードを書かずに解析が進みます。さらに少量データでも精度の高い解析が可能です。農業や畜産ではそもそもデータが少ないため、これは非常に大きな利点です。
予測精度はいかがでしょうか。
卵判別の研究では予測精度が85〜90%に達しました。従来の吸収スペクトル法だけでは80%前後でしたから、大きな進歩です。しかもMulti-Sigma®のバージョンアップによって処理速度も大幅に改善されました。以前は一晩かかっていた学習計算が短時間で終わります。
今後の課題と展望
今後のMulti-Sigma®に期待する機能はありますか。
画像や行列データの直接入力ができると助かります。また分類機能の拡充も欲しいですね。和牛の研究では血統や飼料、運動など説明変数が多岐にわたりますので、最適化機能を活かして解析を深めたいです。さらに、農家や研究者が作ったAIを共有し、アプリとして現場で利用できる仕組みに期待しています。農家が条件を入力すれば、最適な飼料量や飼育法が提案されるような形です。
確かに、現場で直接使える仕組みは大きなインパクトがありますね。
はい。農業は地域性が強いので、画一的な生産ではなく、各地の特色を生かしたブランド化が重要です。AIの力でそれを後押しできると考えています。
結び
本日のお話で、AIが農業・畜産における複雑な課題に大きな解決策をもたらすことがよくわかりました。
ありがとうございます。経験や勘に頼ってきた農業を、データ駆動型へと進化させることが不可欠です。Multi-Sigma®のようなツールは、その大きな推進力になると思います。